
はじめに
「いつか自分や家族が認知症になったらどうしよう」。
終活を考える世代にとって、これは避けて通れない大きな不安のひとつではないでしょうか。
これまで認知症は「進行を遅らせることはできても、根本的に治すのは難しい」とされてきました。しかし、近年の研究で「脳に存在するごく微量のリチウム」という意外な物質が、アルツハイマー病をはじめとした認知症に深く関わっている可能性が明らかになりつつあります。
リチウムといえば、これまで精神科領域の薬として知られてきましたが、実は脳に自然に存在し、神経細胞の健やかな働きを支える“必須の微量金属”であることが分かってきたのです。今回の記事では、この研究のポイントとともに、日本や世界で急増する認知症の現状を整理し、終活世代の方々に「未来への安心」につながる新しい知見をお届けします。
脳に隠されていた“リチウム不足”のサイン
2025年8月、米ハーバード大学などの研究チームが「リチウム」と認知症、とくにアルツハイマー病の関連について革新的な成果を発表しました。

研究チームが行ったのは、認知症の人とそうでない人の脳組織を比較する調査です。その結果、アルツハイマー病や軽度認知障害の患者では、脳全体のリチウム濃度が明らかに低下していることが確認されました。
さらに、アルツハイマー病の特徴である「アミロイドベータ斑」が、まるで磁石のようにリチウムを取り込み、周辺の神経細胞に必要なリチウムが不足する現象も観察されています。つまり、病気の進行とともに脳のリチウム環境が崩れ、細胞が十分に機能できなくなる可能性が示されたのです。
マウス実験で見えた“記憶回復”の驚き
この発見を裏付けるため、マウスを使った実験も行われました。リチウムをほとんど含まない食事を与えられたマウスは、認知機能の低下やアミロイドベータの蓄積が加速し、学習能力や記憶が著しく落ちてしまいました。

ところが、別のマウスに低用量のリチウムを含む水を与えると、驚くべきことに認知機能の低下が防がれ、記憶力の回復も見られたのです。しかも、従来の治療薬で問題となっていた吐き気や腎臓への負担といった副作用は確認されませんでした。
特に注目されているのが「リチウム・オロレート」と呼ばれる形態です。通常の薬の1/1000程度というごく少ない量でも十分な効果を発揮し、毒性の心配もないと報告されています。これが人に応用できれば、安全で負担の少ない治療法として大きな可能性を秘めています。
終活世代にとっての意味
終活を考えるとき、財産の整理や葬儀の準備だけでなく、「健康な自分をどこまで保てるか」という視点も欠かせません。特に認知症は、自分だけでなく家族全体の生活や人生設計に影響を及ぼすため、多くの人が強い不安を抱えています。
今回の研究はまだマウス段階であり、すぐに「リチウムを飲めば予防できる」というものではありません。しかし、これまでの「認知症は治らない」という常識に風穴を開けた点で、終活世代にとって大きな希望の光となるはずです。
日本に広がる認知症の波

2025年現在、日本の認知症患者はおよそ675万〜700万人。65歳以上の高齢者の5人に1人、つまり20%が認知症になると推定されています。高齢化の進行により、この割合はさらに増えていくと予測されており、「誰もが無関係ではいられない時代」に入っています。
症状は記憶障害だけではありません。時間や場所の感覚が失われる「見当識障害」、物事の段取りができなくなる「実行機能障害」、さらには妄想や幻覚、暴言や暴力といった行動・心理症状も現れることがあります。本人だけでなく、介護する家族の生活も一変してしまうのが認知症の厳しい現実です。
その一方で、医療や介護を支える人材は不足し、社会的な負担は急速に膨らんでいます。国は「新オレンジプラン」と呼ばれる施策を推進し、早期発見や予防に取り組んでいますが、根本的な治療法の確立には至っていません。
世界に広がる課題
認知症は日本だけの問題ではありません。世界では2021年時点で5,500万人を超える患者がおり、2030年には7,800万人、2050年には1億3,900万人に達すると予測されています。
経済的な負担も深刻です。すでに世界全体で年間1.3兆ドル(日本円でおよそ150兆円)にのぼるとされ、その多くが家族による介護に支えられています。特に女性が介護を担うケースが多く、社会全体の労働力や生活基盤にも大きな影響を及ぼしています。
新しい治療戦略としての可能性
こうした現状を踏まえると、今回のリチウム研究が示す意義は計り知れません。
第一に、認知症の発症や進行に「脳内の微量金属バランス」が深く関わっていることを明らかにした点です。これまでの治療はアミロイドベータやタウといった病変そのものを直接狙うものでしたが、リチウムを補うことで「脳の環境そのものを整える」という新しい視点が生まれました。
第二に、早期診断や予防にもつながる可能性です。血液や体液のリチウム量を測定することで、認知症リスクを早い段階で察知できるかもしれません。これは、将来の終活計画を立てる上でも重要な「自分の健康リスクを知る手段」となるでしょう。

終わりに:未来に希望をつなぐために
もちろん、人間への応用にはさらなる臨床試験が必要です。今すぐに薬として利用できる段階ではなく、研究者たちも「自己判断でリチウムを摂取するのは危険」と注意を呼びかけています。
それでも、「脳内のリチウム不足を補うことで、認知症の進行を防ぎ、場合によっては記憶の回復さえ可能かもしれない」という事実は、これまでの常識を大きく覆すものでした。
終活世代にとって、この研究成果は「未来に備える安心材料」となるはずです。自分や家族の人生の終盤を少しでも穏やかに、希望を持って迎えるために、科学は着実に前進しています。
私たちができることは、このような新しい知見に関心を持ち、日々の生活習慣を整え、そして「いつか訪れるかもしれない変化」に備えることです。リチウム研究が切り開く未来は、認知症との向き合い方を大きく変えるかもしれません。

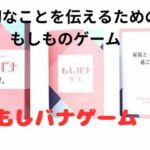
コメント